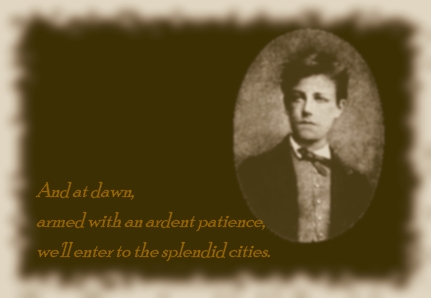第九章 ナントの混乱

<scene 19 ナント>
ナントでも宿はなかった。
そして、酷い幻聴が出てきた。
車の通行音が増幅され、しかもエコー・エフェクトが掛かり、ギャーンという聞くに堪えないものになっていた。
往来を走る銀色の高価そうなアルミホイールが恨めしく見えた。
通行人が、(そんな音ばかり聞いていたら気が狂うぞ)とテレパシーで言った。日本語だったし、それも幻覚であることは知れていた。
もうその時点で頭などおかしいのだから、幻聴にご忠告いただくのも片腹痛いことだった。
それに、好きでやっているわけではなく、一旦そういうバイアスがかかると、増幅こそすれ、止める方法などなかった。
精神病院に行く? 論理的にいって、そんなバカげた考えはなかった。
よし、それで緩和薬を買って飲んだからといって、症状がツライ時にその「緩和」ならされるだろうが、もし、人間の自然治癒力によって症状が改善されようとする時が訪れても、投与され続ける緩和薬と均衡するために、脳もまたホルモンを出し続けなければならなくなる。
むしろそれは、スキゾフレニアを一生治らない持病にしてしまうことを意味するのではないか。
現在に至っても、精神病の治療薬というものは存在しない。あるのは症状を緩和させる薬剤だけなのだ。
いつ終わるともしれない戦いだったとしても、耐えるしかなかった。
その夜は、シャッターの降りたショッピング・モールから張り出した屋根の下、大きな四角い柱の陰で座って寝ることにした。
ノイズから気をそらすために思考した。
ニコラ・テスラの地球共鳴。
これは50年後にシューマン共振7.83ヘルツによって裏付けられるが、地球が共鳴りする周波数があることに着目している。
身近な例でいえば、ギターのサウンドホールに向かってA=440ヘルツの声を発声すると、A弦が共振してブーンと音を立てる。
ところで、現代文明は50ヘルツから60ヘルツの周波数を使って、「電線」によって送電している。これを、電線ではなく、地球全体の共振周波数を使って送電しようと考えたわけだ。
ならば私は、天候操作の媒介を、地球の共振周波数で送信可能なものと考えることはできないか?
左手首には、バーテンダーに付けてもらった”Be Cool”のミサンガ。これも永遠からの来訪者がくれたメッセージだったろうか。
次の日の朝、6路線ほどあるホームに立った。
(この駅のホームは、屋根がないな)
と見やっていた。別に珍しいことではないが、この規模の駅としては不釣り合いに見えた。
すると、フッ、フッ、フッと聞こえない音でも立てるように、屋根が次々と出現した。現実と区別のつかない幻覚も困りものだが、この種の派手な脳内パフォーマンスにも驚かされる。
私はまず近場に出来た鉄柱に触ってみた。
(こいつは一体、どこから来たんだ)
私の手は、鉄柱をすり抜けたりしなかった。
念のために、私は一番離れた路線に移動し、それも触ってみた。
明るい青色のペンキで塗られた鉄柱は、冷たい感触を放っていた。押してみても微動だにしない。
考え方はふたつある。それは最初からそこにあって、幻覚によって目隠しされていたのか、あるいは幻覚によって強固な物体として作り出されたか。
屋根を見上げると、その向こうに青い空が見えた。
鉄柱に、体重をかけた右手でもたれて、うつむいた私の姿は、他人からどう見えたことだったろう。
☆
─── スピリチュアルなコンバットは人間のバトルと同じくらい残酷だが、道理に適うビジョンは神のみの喜び。
ランボーの詩集「地獄の季節」の最終部分からの引用だ。
彼は、望んだ魔術修行の為には、自ら精神を壊すしか方法がないと見定め、実行した。
それはポール・デメニー宛書簡にくわしいが、正確な推測で書かれた。自らが斃れる可能性もあらかじめわかっていた。そして剛胆にも、それを厭いもしなかった。
華々しい幻覚についてランボーは、例えば母音に色を見るような共感覚、また湖底にサロンを見るような幻視、などのことは書いている。
一方で、誰しも書きたくないことだろうが、病状もあったはずだ。
そしてそれは、感覚としては戦いに近いものになる。
例えば前述したような私の「車の幻覚的通行音」などは、精神的な戦いの最中であるがゆえに、ともすれば自分への攻撃に感じられてしまう。
「おれに仕返し出来たらなあ」と、ランボーは述懐している。
言うまでもないが、できないから臍を噛んでいるわけだ。
加えて、スキゾフレニアあるいは認知症でもそうだが、被攻撃妄想を肥大化させ、単純な敵味方の構図を身辺に作り上げてしまうことが典型的にある。
無論、必要なのは「道理に適ったビジョン」である。
ただの精神病シンドロームを、誰かからの攻撃だと考えたとしても、反撃できないのなら、敵対に意味がない。
けれども、ランボーがそれを神の喜びとしていた点で、最終的にランボーはキリスト教の神を信じていたのかもしれないと感想する。
私も特定の神ではなくて、何か大きな存在という意味でなら、信じなくはない。
20世紀に入って死んだと言われたのは外側にいる神であって、内側の神性すなわち審判者たるセルフが、今も精神の中心にいるのであれば。
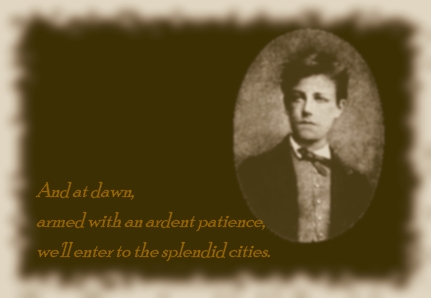
─── しかし、今は前夜だ。すべての力ある感応とリアルな優しさなら受け入れよう。そして払暁に、焼けるような忍耐で武装して、われわれは輝く市街へ入っていこう。
これも詩集最終部分からの引用だ。緊張感の漂う感動的な場面で、詩として美しい。
優しい感応なら受け入れると言っているので、傷口に塩を塗り込むような種類の感応は除外されている。そう、詩集地獄の季節でランボーが対峙したのは、タチの悪い女の悪魔(これもアニマの一面だ)であって、全編が彼女との戦いの物語だったのだから。
そして、文の主語が複数形である。書き手が読者の参加意識を高めるために、主語を複数形にすることはママあるが、この場合は違うだろう。すなわち、アニマを含むか含まないかで、一人称単数と複数を分けていると思う。
そして、地獄の季節の最終行。
─── そして私にはひとつの魂とひとつの肉体の内に真実を所有することが許されるだろう。
第五章女たち(アニマ)に引用した「デリア1(譫妄)Foolish Virgin」から見て、ランボーの精神に聖処女風のアニマが棲んでいたことは明白なので、ひとつの魂と言っているのは興味深いところ。
☆
ところで、アニマが自我意識と接触するようになったからといって、それは本質的には無意識に属している。
そして無意識は時間を持たない。
これは取りも直さず、因果律の記憶を持たないことを意味する。
たとえば犬も同様であり、だから「お手」を教えている時に、先ほどまで出来ていたのに次はできないという現象がおこる。
そして、興味深いことだが、自閉症から帰還した男性の述懐として、時間軸に沿った記憶がなかったという報告がある。記憶が直線的には整列せず、ひとつひとつが、たとえれば子供部屋の床に散らばったおもちゃのようにとりとめなくも存在していたということになる。
もし自我が、何らかの理由で無意識の淵に沈んでしまったときには、そうした自閉症になるのではないか。
つまり何が言いたいのかといえば、ひとつの推理としてだが、アニマの記憶もそのようなものと思っている。
なぜなら、表に出てきてしまった私のアニマも、つい先ほどのことを覚えておらず、「それはなあに?どういうこと?」などとと問い直すことが都度都度あったからだ。
それが起こると、こちらとしては、キャラがこれまでと代わってしまったのかと疑わざるを得なかった。いや本当に替わっていた可能性もあるのだが。
だから、ランボーがアニマに対して多くの名前をつけていたことも十分理解できる。例えば、「イリュミナシオン」の「献身」では、ルイーズ・ヴァーナン・ド・ボーリンゲム尼、レオニー・オーボワ・ダシュビー尼、リュリュ(悪魔)などの女性名を並べ、懐かしそうに献辞を贈っている。
けれども、そのようなアニマのストーリーに絡めとられてしまうと、快復はむつかしくなる。
スピリチュアル・コンバットにおける最後の罠は、自分自身だ。
結局のところ、アンドレ・ブルトンによってランボーの霊的な遺書と評された「夜の大部屋」を見ても、区別のつかないことになってしまった。
☆
ここで、詩集「地獄の季節」と同時期か、より後に書かれたとされる「イリュミナシオン」から、「ジニー(Genie)」を掲載しよう。多くの人が好む詩だと思うが、私もそうだ。私の心の旅は、ここから始まった。
フランス語のジニーは英語に置き換えればジーニャス(天才)だが、この詩は日本ではふつう「精霊」と邦訳される。勿論、仏語にせよ英語にせよこの言葉は精霊という意味を含んでいる。
日本にも歴史的に中国の漢字が移入されたように、英語と仏語の単語はかなりの程度照応関係にあり、同じ綴りの単語も少なくない。ただし、方言的なニュアンスの違いはあって、英語の genie という単語にはランプをこすると出てくるアラビア風の魔人の意味があり、語学に堪能なランボーはそのイメージにフックしたと私は思っている。
一般に、「精霊」の「彼」は神だと解釈されているが、私は「彼」をランボー自身と考えて翻訳した。
ならば、詩の語り手は「精霊」(ユング風に言えばアニマ)となる。
訳出は、句読点を原文に忠実に翻訳したつもりなので、読みにくい文章になっている。なぜなら、朗唱が前提されていると考えられ、その場合には、長いフレーズでも一息で言い切りたいところ、逆に短く畳み掛けたいところがあるだろうからだ。
また、フランス語では一人称複数形は日本語のように区別されないが、アニマ達の「われら」と、ランボー自身も含めた「われわれ」があると考えられたため、翻訳に当たっては区別している。
( )内の文は、精霊のシュプレヒコールと考えて、凡そ間違いではないと思う。
「精霊」
彼が情愛そして贈りものだというのも事実トリハダの冬に館を開け放ち夏の噂でも、彼こそ飲み物と食べ物を浄化した、彼こそ魅惑の隠れ家であり恍惚の超人的佇み。彼は愛情と未来、力と愛はわれらのもの、怒りと憂愁の中に立ち、われわれは空の向こうに嵐をそしてエクスタシーの旗めくのを見るのさ。
彼は愛情、再発明された完璧な尺度、予測できない最高の理性、そして永遠 (致命的な性能で愛される機械だ)。われわれはみな彼とわれらの授かり物に戦慄した。(おおわれわれの健康の享受よ、能力の開花よ、エゴイストの感覚と情熱は彼自身のために、彼こそがわれらに愛された無窮の命・・・)
そしてわれらは各々を召喚して彼の旅・・・もし崇拝が去れば、音、お約束の、音、「下がりおれその迷信、そんな旧式の肉体、こんな家庭そんな世代。そんなものはこの時代に滅びたのだぞ!」
彼はどこへも去りはしない、どこかの天国から再臨することもない、女たちの怒りや男たちの騒動そして全ての罪に救済を与えることもない(なぜならそれは成就した、彼の生によって、そして彼が愛されることによって)
おお その息吹、その頭脳、その疾走(恐るべき迅速さ完璧なフォームとアクション)。
おお 肥沃な精神と無辺の領域!
彼の肉体! 請け戻した夢、新しい暴力で十字架の恩寵を砕く!
彼の視力、その視野! いにしえの跪拝と刻まれたその苦痛を見抜く。
彼の生活! 全ての不実な音を解放しより強力な音楽の中へ展開する。
彼の歩み! 古代の侵略よりも雄大な移住。
おお 彼とわれらに! 失われた慈愛より親切な傲慢。
おお 世界よ! ─── 新しい逆境と透明な歌声よ!
彼はわれらの全てを知りわれら全てを愛し、わかるだろう、この冬の夜、岬から岬へ、揺籃する地軸から城へ、民衆から大地へと、見るのだ見るのだよ、力と感情が失せたら、呼びかけてつながり、また戻る。そして潮流の下また高き雪の砂漠、ついていこうじゃないかその視野、その苦悩、その体、彼の光芒に。
【注解】
アニマは、ユング心理学では、普通、夢や他者への投影として体験されるといわれるのだが、幼少期から副人格としてのアニマを経験したユングが、普通のことだけを語っていたと考えることはない。心の内なる声が聞こえるケースもある。私がこの小説でアニマと呼ぶ者は、それに限定される。
第十章へ進む →→→
|